研究結果:2021_感染拡大・抑制シミュレーション
感染拡大・抑制シミュレーション
-
ワクチン接種プランニング(②を改訂) 感染抑制もオリンピックの主戦力も「自然で迅速なワクチン普及」
2021.06.16
機 関
東京大学大学院工学系研究科
研究者
大澤幸生
タグ
関連する研究資料

機 関
東京大学大学院工学系研究科
研究者
大澤幸生
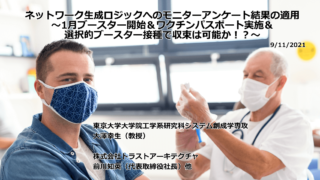
機 関
東京大学大学院工学系研究科
研究者
大澤幸生
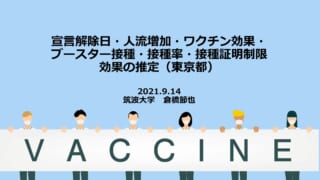
研究者
倉橋節也
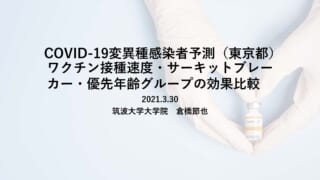
研究者
倉橋節也
研究結果:2021_感染拡大・抑制シミュレーション
ワクチン接種プランニング(②を改訂) 感染抑制もオリンピックの主戦力も「自然で迅速なワクチン普及」
2021.06.16
機 関
東京大学大学院工学系研究科
研究者
大澤幸生
タグ
関連する研究資料

機 関
東京大学大学院工学系研究科
研究者
大澤幸生
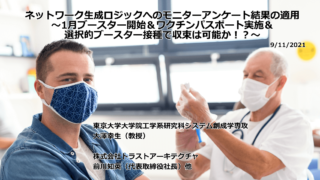
機 関
東京大学大学院工学系研究科
研究者
大澤幸生
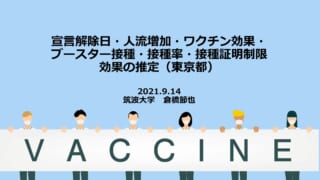
研究者
倉橋節也
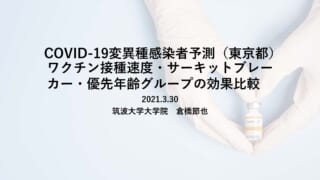
研究者
倉橋節也