研究結果:2022_感染状況シミュレーション
感染状況シミュレーション
-
第6波における重症化率・致死率 −2022年1月に提示した見通しの事後検証−
2022.06.22
機 関
東京大学大学院経済学研究科
研究者
仲田泰祐
タグ
関連する研究資料
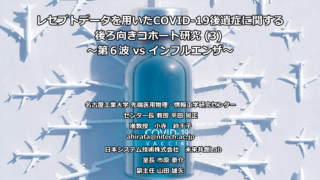
研究者
平田晃正
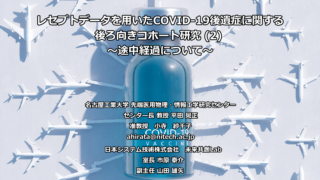
研究者
平田晃正
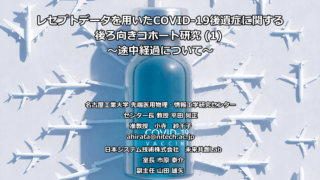
研究者
平田晃正
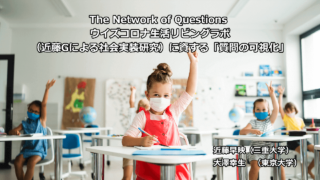
機 関
東京大学大学院工学系研究科
研究者
大澤幸生
研究結果:2022_感染状況シミュレーション
第6波における重症化率・致死率 −2022年1月に提示した見通しの事後検証−
2022.06.22
機 関
東京大学大学院経済学研究科
研究者
仲田泰祐
タグ
関連する研究資料
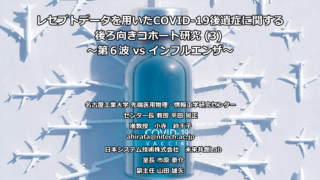
研究者
平田晃正
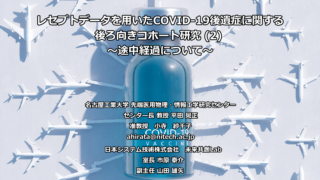
研究者
平田晃正
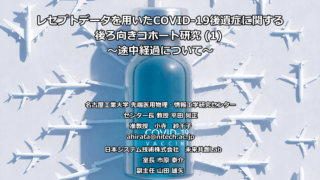
研究者
平田晃正
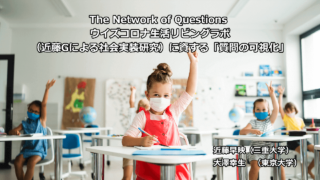
機 関
東京大学大学院工学系研究科
研究者
大澤幸生